3.0
大原美術館所蔵の主要な作品が予想以上に展示されていました
ここ数年の中之島香雪美術館の展覧会は傾向が変わってきました。
日本各地の美術館の所蔵品を大阪の地で展示!な感じとでもいうのでしょうか。
それ故に足を運ぶ人も増えてきたのではないで… Read More

美術館・展覧会情報サイト アートアジェンダ - 日本全国321の美術館・博物館と607の開催中&開催予定の展覧会をご紹介中!
阪神間在住。京都奈良辺りまで平日に出かけています。美術はまるで素人ですが、美術館へ出かけるのが大好きです。出かけた展覧会を出来るだけレポートしたいと思っております。

六甲ライナーに乗ってお久しぶりに六甲アイランドへ行ってきました。六甲アイランドには、3つも美術館があります。…

2026年始動しました。早々に大きな地震のニュースに心が痛みます。神戸の震災から31年目の日ももうすぐです。…

東洋陶磁美術館(通称:Moco)コレクションの中核をなすのは、皆様もご存じの安宅さんの審美眼で蒐集された中国・韓国陶磁コレクションです。この「安宅コレクション」が住友グル…

会期末となりましたが、この秋の忘れ物回収のように京都市京セラ美術館で開催中の特別展「民藝誕生100年—京都が紡いだ日常の美」へ行ってきました。1925年「民衆的なる工芸=民…

寛永3年(1626)9月6日徳川幕府の大御所・秀忠と三代将軍・家光は、後水尾天皇を二条城にお迎えして、9月10日まで5日間に渡っておもてなしを行いました。大坂夏の陣で豊臣家が…

京都五山(別格: 南禅寺、第一位: 天龍寺、第二位: 相国寺、第三位: 建仁寺、第四位: 東福寺、第五位: 万寿寺)の二位に列せられる相国寺は、京都の真ん中、京都御所の北の門、…

藤田美術館は、3つのテーマで展示され、毎月1つのテーマが展示替えとなり3ヶ月で全部の展示が替わるシステムです。今月のテーマは、「遊」「虫」「誂」です。今月末で「誂」の…

今年は上村松園生誕150年ということで、松園の作品を目にすることが多かったです。本展も福田美術館が所蔵する松園作品を中心に美人画の軌跡をたどろうとする企画展です。上村…

興祖微妙大師六百五十年遠諱記念特別展「妙心寺 禅の継承」@大阪市立美術館の情報が公開されました。会期は、2026年2月7日(土)~4月5日(日)です。※掲載画像は、暑さの残…

2023年5月末に休館、2024年8月に閉館した東京都青梅市にあった「澤乃井櫛かんざし美術館」から約5,000点の装身具の寄贈を受けたことを記念する展覧会です。細見美術館はこれま…
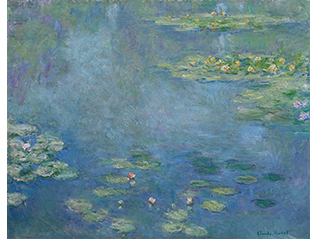
3.0
ここ数年の中之島香雪美術館の展覧会は傾向が変わってきました。
日本各地の美術館の所蔵品を大阪の地で展示!な感じとでもいうのでしょうか。
それ故に足を運ぶ人も増えてきたのではないで… Read More

3.0
現代アート、AAさんでの感想やレポートを拝読して出かけていきます。
映像が多いんだな。映像作品結構苦手な私。途中退出できず、じっくり向き合う作品があるんだなと思いながら出かけていき… Read More

3.0
年末大阪中之島美は賑わっていました。
アールデコなのか様々に展開を広げたシュルレアリスムへなのか着物姿のご婦人が多かったです。
そこで布で作られた7つの門は写真映えがするようで、多… Read More

3.0
今年最後かなぁと思いつつ、大山崎山荘美術館まで行ってきました。
毎年秋の紅葉の時期に出かけるのですが、外国人観光客も増えて回避。
AAさんからチケプレのプレゼントを頂戴してお天気の… Read More

3.0
私もアバウトさんやくつしたあつめさんのレビューを拝読して、京都へ行ったとき、寄れる時はdddへ伺うようになりました。
もう全くアバウトさんのレビューの通りで
漢字のなかでも中国本土の… Read More

3.0
会期末になってしまい、12月の平日の午後には、私も含めて来館者は中高年の女性です。
子どもに詠み聞かせた絵本の中にきっと谷川俊太郎の絵本もあった方々だと思いました。
秋真っ盛りには… Read More

4.0
「民衆的なる工芸=民藝」という言葉が生まれて100年。ここ数年「民藝」の展覧会が開催されることが多く、関西圏で開催されるものの多くを観てきました。「民藝」またかぁの感があったのです… Read More

3.0
美術館近くを流れる夙川は桜で有名ですが、松の木も多い。
「松」は、吉祥も表しさまざまに表現されてきました。
市政100周年を祝って「松」をテーマにした展覧会で、絵画や硯箱などの蒔絵や… Read More

3.0
柳宗悦が「民藝(民衆的工藝の略)」を提唱してから100年を迎え、昨年から「民藝」の展覧会が多く開かれています。、名も無き職人による用途に即してつくられた「手仕事」、生活道具の中に美… Read More

-
私も展覧会のメインヴィジュアルを見て行きたいと思いました。
まさに昭和生きた画家、大正14年(1925)年生まれということは昭和元年でもあるので。全く知らない画家でした。美術史家・山下… Read More

富山県
4.0
市電の走る街が好きです。
阪神間を出るのはコロナ禍前18切符でウロウロしていた頃以来でとっても久しぶりでした。
かつては21美にも18切符で出かけましたが、今回は敦賀までサンダーバー… Read More

大阪府
5.0
国立民族学博物館(みんぱく)は、1974年6月7日に創設され、2024年に創設50周年を迎えました。1977年に竣工して11月に一般公開となりました。
博物館の設計は、黒川紀章です。万博公園の中… Read More