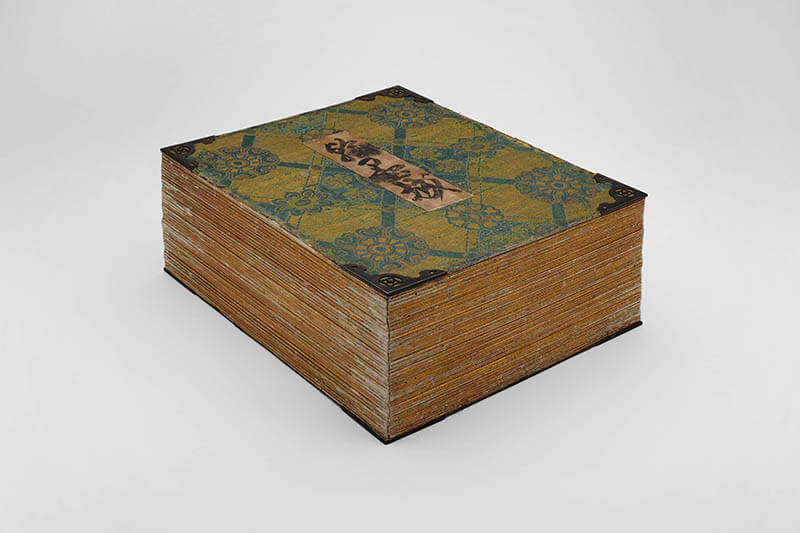5.0
尾形光琳の「紅白梅図屏風」
尾形光琳の国宝「紅白梅図屏風」を見る事を楽しみにMOA美術館に行きました。「紅白梅図屏風」を見る前に、杉本博司の「月下紅白梅図」があり、周りのお客さんが「こんな色だったかな」と困惑しているのを楽しんでいるかのように思われる展示経路ですが、海景シリーズのモノクロ写真を思い出す作品でした。モノクロにすることで、本物の「紅白梅図屏風」を月の下の明かりで見るとこのように見えるのではないかと想像させる、そのアイディア、さすが杉本さんの想像力、リスペクトを感じる作品でした。
そして、いよいよご対面。尾形光琳の「風神雷神図屏風」を初めて見たときに受けた印象と同じ印象を今回も受けました。右隻の若い紅梅の幹は細く濃い墨で描かれ、左隻の老いた白梅の幹は太く、墨は薄く、紆余曲折の人生を折り返し伸ばした長い枝で表現し、老若の対比がみごとでした。ただ、老若梅ともに枝先には数多くの梅の花が咲き誇り、いつの年代も人生を輝かせていけることを象徴しているかのようでした。また、中央に流水も上は細い川幅で濃い墨で描かれ、右上から左下へ広がる川幅とともに墨の色も薄くなっていました。水流の渦巻きは、琳派の特徴である意匠性で表現、レオナルド・ダ・ヴィンチを彷彿とさせる渦巻き表現は、長年の観察結果から生まれたことを感じさせるものでした。