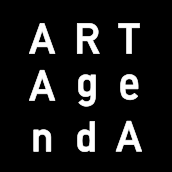特別展「大安寺のすべて―天平のみほとけと祈り―」
奈良国立博物館|奈良県
開催期間: ~
- VIEW705
- THANKS1
あんまり聞いたことないけど「大安寺」ってどんなお寺さん?
展覧会のチラシや美術館広報誌などに目を通しても
感想のタイトル通り「大安寺」で私の中では????ということで、友の会解説会に参加してきました。
担当研究員さんから展覧会の構成と見どころ、仏教史における大安寺などについて30分ほどお話しいただきました。
この30分ほどのお話で、どんなところに注目するといいのかヒントになりました。
「大安寺」今では1つのお堂が残っているだけですが、こうなるまでのお寺の歴史を今に伝わる7体の仏像や発掘調査や文書などで紐解く展覧会です。
文書展示が多くて、閉館までの1時間半、私にはもう少し時間が欲しかったです。
大安寺の歴史は古く、飛鳥時代聖徳太子まで遡れるらしいのですが、
どこにも書いてある説明は「わが国最初の天皇発願の寺」つまり、それ以前は皇族などによる私のお寺が建てられていたということです。
舒明天皇が「百済大寺」というお寺を建て始め、その後は何度も移転し、お寺の名前も改名され、8世紀の初め平城京に落ち着き、奈良時代の中頃には「大安寺」と呼ばれるようになったそうです。
南都七大寺の1つで、東大寺や興福寺と並ぶ大規模な筆頭大寺院でした。
奈良時代の木彫像7体が今も残り、7体全部が展示されます。馬頭観音像は後期展示です。それぞれに腕やお顔は後補ですが、細部に彫り出した飾りにご注目!
唐三彩の「陶枕」、枕に使われたかはいささか疑問ですが、色鮮やかな唐三彩がお堂の中を彩ったのではないかとのお話でした。
大きな「風鐸」、軒先に吊り下げる「風鐸」その大きさから寺院の大きさも推し量れるということでした。
大安寺のご本尊「釈迦如来像」は中世から近世で失われてしまっていますが、多くの文書にそれはそれは素晴らしいお像だったと記されています。
薬師寺さんの「薬師如来像」は大安寺の釈迦如来像の次に美しいなーんて書かれているそうです。
大安寺の仏教史での大きな役割として、国内外の偉い僧が集まる国際的な学究道場だったみたいです。
例えば、東大寺大仏の開眼の導師だったインド僧の提僊那なんかもいて、大陸から来日した僧たちはまず大安寺へ向かったそうで、奈良時代には1000人の国内外の僧が集まったと伝わっているそうです。何語で会話していたのかしらとも思ってしまいます。
しかしながら平安時代の中ごろから朝廷の管理が薄れ、寺院は自分たちで経済活動を行っていくようになると、大安寺の規模は縮小していきます。
経済的なネットワークを持つ寺院が強くなり、大安寺には興福寺と律宗の西大寺の2つのグループが形成され力を持つようになっていました。
度重なる火災や地震や盗難によって復興するめどもなく廃れていったようです。
興福寺の四天王像も元は大安寺にあったそうで、折しも現在興福寺北円堂が春季公開中です。
運慶展@東博で見た方も是非もう一度運慶仏を間近でいかがでしょうか。
大安寺展を観終わって、改めて法隆寺や正倉院が今にあのようにあることは凄い!!と感じました。
夕刻の奈良公園は静かでいい感じでした。この時間帯も悪くないなぁ。
余談ですが、修学旅行生なのでしょうか、お昼間奈良公園は学生さんがいっぱいいました。
頭に”せんとくん”よろしく、鹿のカチューシャした子も多くて、
私は「えっ!!!」ディズニーランドと違うよここはと思ってしまいました。
- THANKS!をクリックしたユーザー
- Audreyさん
- 1
- BY morinousagisan